フランスの作家オリヴィエ・ブルドーさんの『ボージャングルを待ちながら』の書評を担当しました。集英社「青春と読書」10月号にて。
「うたかたの日々」と「グレートギャッツビー」の間に 菅原敏
本を開けばレコードが静かに回りだし、ピアノがこぼれ、ゆるやかなリズムで言葉たちはステップを踏み始める。そしてニーナ・シモンの優しくて少し悲しい歌声がページの間を満たしてゆく。擦り切れた靴で高く高く飛び、軽やかに踊るミスター・ボージャングルの歌。
ボリス・ヴィアンは、この世界に必要なのは可愛い子との恋愛とデューク・エリントンの音楽だけだと言っていた。そしてオリヴィエ・ブルドーは、この曲「ミスター・ボージャングル」と愛のための美しい嘘だけが必要だと教えてくれる。ターンテーブルに乗せる唯一の価値のあるレコード、ダイヤモンドの針を落とすにふさわしい曲。
現実を軽やかに無視するミューズのような女と、彼女を毎日違う名前で呼ぶホラ吹き男。その二人が結婚し、毎夜パーティをしながら息子の“ぼく”を育てていく。「真実が退屈か悲惨なら、嘘をこしらえて楽しくしなさい」。風変わりな3人の、ユーモアと愛あふれる日々。だが、やがて砂糖菓子のように母親の心はその輪郭を失ってゆく。カクテル片手、何リットルもの点滴を腕で飲み干し、頬が覚えている涙の跡。パーティが始まった時から彼女の狂気は脱線し、いずれ全てを清算する日がくることを知っていた父親。「何があろうと働かないで」と現実世界にテーブルクロスをかけ、星をつかむほど高く高く軽やかに最後のダンスを踊った母親。スペインの小さな城、湖面にたゆたう結末と、嘘と嘘の間に隠れていた最後の約束に胸を貫かれる。
悲しみをひたかくすユーモアと愛。泣きながら笑い、飛びながら地面に這いつくばり、転がるように読み終えた私は、この一編の詩のような純愛の物語を本棚のどこに挿すべきかと考える。そして本棚三段目の特等席で「うたかたの日々」と「グレートギャッツビー」の間にそっと挿し込んでみる(この本は自伝的な体裁を取りつつも、フィッツジェラルドと妻ゼルダへのオマージュとして作られたものだという)。二冊の間でウトウトとくつろぎ、居心地はとても良さそうだけれど、この先幾度となく私はその眠りを妨げ、ページの中で何度も繰り返しあのレコードを聞くのだろう。
すがわら・びん(詩人)
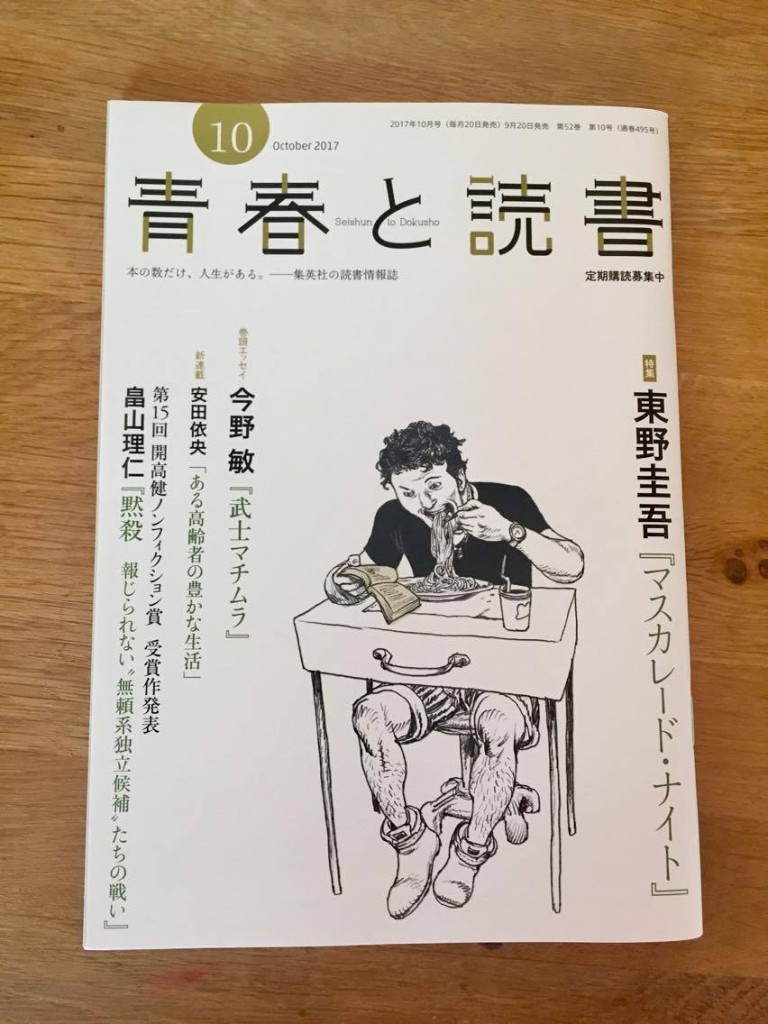



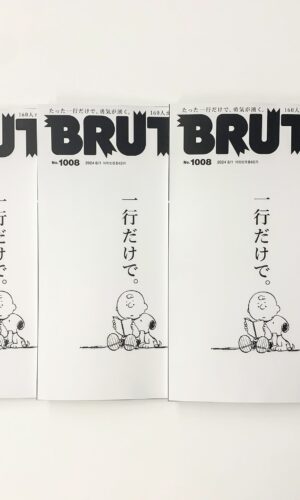


Comments by sugawarabin